●略歴
1995年 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 (修士(保健学))
2001年 千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了(博士(学術))
2004年 千葉大学文学部着任
●研究テーマ・研究対象
生態人類学という分野、つまり生業(生産し、交換し、消費すること)や人口動態の記述、分析を通して、環境と人間のかかわりを考察することを専門としています。具体的には、パプアニューギニアでバナナの品種と栽培方法を聞いて回ったり、マレーシアで狩猟採集の生産物によって世帯の生活が維持できるかを分析したりしています。そのような生業活動の多様性が環境の差異にもとづくのか、あるいは社会文化的に構成されているのかを考察すべきテーマとしています。また、人口増加/減少のような人口動態の集団ごとの多様性について、生業活動、あるいは人間関係から分析することも主なテーマです。パプアニューギニア(特にボサビという言語集団)、マレーシア(特にバテッ、ムンドリッという言語集団)が大学院時代からのフィールドですが、千葉県をはじめとする日本国内における研究も進めています。
●文化人類学を研究するきっかけ
もともと霊長類の生態に興味があり、生物学的なフィールドワークを志していました。学部生時代に、屋久島でサルの観察のかたわら地元の方々の話を聞いたり、人類学の先達から世界各地の文化・社会を学んだりするうちに、文化の多様性の方に興味を持つようになりました。また、様々な偶然が重なってパプアニューギニアとマレーシアが主な調査地になった訳ですが、結果的には両地域ともに自分にとても合ったフィールドであると思います。ひどい花粉症なので、乾燥地よりは 熱帯雨林の方が結果的に体に合っていたし、さらに両地域ともに珍しい食べ物がたくさんあり、研究目的としても個人的嗜好としてもフィールドとして理想的なのです。
●研究で印象に残ったこと
ニューギニアで加工されていないコンニャクイモを食べたことがあるのですが、非常に不味かった!コンニャクという加工技術の素晴らしさに気付かされた訳です。コンニャクイモだけではなく、ニューギニアは珍しい食材(昆虫や有袋類などなど)の宝庫であり、食べること自体が非常に楽しい経験です。いかんせん調味料を使わないなど加工方法にこだわりがないので、素材の味そのままなのが物足りないところです。逆に、マレーシアは多彩な調味料の宝庫であり、「おいしさ」へのこだわりに感嘆させられます。特にラクサン(冷やし魚汁にチクワブのようなものを入れた料理、ラクサでは無い)が好物です。バナナの研究者として、世界各地の様々な種類、様々な味のバナナを食べ比べられるのも役得です。
●おすすめの本
上橋菜穂子 『獣の奏者』 2006年 講談社
上橋菜穂子 『精霊の守り人』 2002年 新潮文庫
上橋氏は著名な作家ですが、同時に文化人類学者(かつオセアニア研究者)でもあります。小説の内容にさりげなく文化人類学的思考や知見がふまれており、肩ひじ張らずに人類学に触れることができます。人類学を全く意識せずとも、そもそも小説として非常に面白い著作なのでお薦めですね。
中島敦 『光と風と夢・わが西遊記』 1992年 講談社文芸文庫
中島敦の南洋物は、今は失われたオセアニア世界の姿、あるいは今も失われていない日本人からオセアニアの人びとへの視線が読み取れて面白いです。南洋物はこの本だけではないので探してみて下さい。「光と風と夢」はスティーヴンソン (『ジキル博士とハイド氏』などの作者)の伝記でもあり、「わが西遊記」はオセアニア全然関係なく、カフカっぽい中島敦の思考が垣間見れて興味深いですね。
ウィリアム・ギブスン 『ニューロマンサー』 1986年 ハヤカワ文庫
人類学とは全く関係ないですが、千葉大学に在籍するならこの本含めた「スプロール三部作」は必読です。サイバーパンクの中心は、ロスでもなくサイタマでもなくチバなのです。あったかもしれない未来の千葉を見聞してみて下さい。
●おすすめの授業
ユーラシア文化論(日本ユーラシア文化コースの授業)、日本民俗学(国際教育センターの授業)。また、認知情報科学専修の授業には、生態人類学に通じる内容が多く含まれています。
●人類学をこれから学びたい人へのメッセージ
世界の面白いこと、おいしいものを探しに行きましょう。それが多様性の理解への第一歩です。
●主な業績
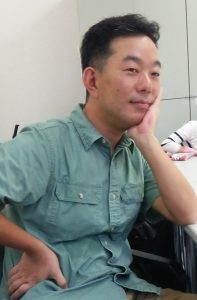
研究室で育てている小笠原諸島産キングバナナ


